ナットは指板の先端と糸巻き箱との間にニカワ付けされ、その上面に彫られた4本の溝により弦がそれぞれの糸巻きに導かれていきます。
指板と同様に演奏者の手に直接触れるところであり、また弦というバイオリンにとって重要な部品をセットする役目を担っているので、その形状・寸法には正しい知識が必要となります。
**********
ナットの形状は、
厚み:糸巻き箱と板指の間に糸巻き箱に被さることなく付けられますので、この間の寸法である6mmにセットします。
幅 :指板の狭いほうの先端に指板両端よりはみ出すことのないようにしますので、指板の先端の幅の寸法である24.0mm~24.5mmにします。
ここで数値に範囲を持たせたのは、製作者の考えで異なることがあるので、そのことを考慮しましたが標準的にはこの範囲を超えることはないと
考えます。因みに、これは演奏者の手の大きさ及び好みによるところに依存します。
高さ :指板先端の高さより高くなくてはならないことは明確ですが(そうでなければ弦が指板にあたってしまいますので)、では、どのくらいかということが
数値で表現することがなく経験的に“このくらい”で仕上げています。目安としては、G線で1.5mm強、E線で1.0mm強といった辺りかと思います
(参考までにということで…)。ここに弦をセットするための溝を掘りますので、弦と指板との隙間はこれらの数値より0.5mm程度(溝の深さ)小さく
なります。溝の深さは目安としてセットされる弦の太さの半部程度と考えていますが、弦が指板からどの程度離れているかということは演奏に大きく
影響するところですので、この数値は重要なポイントとなります。 “あまり大きくしない” ということが一つの考え方かと思います。
以上の3点によりナットの形状を考えます。
ここで幅に関しましては完成形状よりも数ミリ余裕をもたせておきます。その理由は、G線とE線がペグに巻かれる際に弦が糸巻き箱の内側にあたる傾向があり、これを避けるために糸巻き箱の内側を少し外側に広げるように仕上げます。それに伴いこの部分の糸巻き箱の肉厚が薄くなってしまうのを防ぐため糸巻き箱外側形状をやはり少し外に膨らませるように仕上げます。その際、この部分と接しているナットもその形状に合わせるようにしますので24.5mmよりも大きくする必要が出てきます。これは、ネック仕上げの最終作業としてのネック裏側の丸みを形成する時に行いますので、この段階ではこれらのことを考慮して余裕を持たせた状態にしておきます。
以上の内容にそって黒檀を適当な形状に仕上げて用意します。
これは、ナットとして大まかな形状に仕上がった部品が販売されていますのでそれを使用してもよいでしょう。
適当な形状に仕上がったナットとしての黒檀の木片を指板の先端部分と糸巻き箱の間にニカワ付けします。基本的には指板断面(ナットとの接着面)とネック表面(指板との接着面)は垂直ですので、ナットのこの2面に接着される面も垂直になっているはずですが、もしどちらかの面で隙間があるようでしたら隙間のないようにナット面を調整します。ここはクランプなどで固定することが難しい部分なので、しっかりニカワ付けで固定するためにもこの精度は大切な要素となります。この2面に隙間がないことを確認して、それぞれにニカワを付けてナットと指板の接着面をよく摺り合わせて手でしっかり押し付けてから放置します。正確に互いの接着面ができていればこれで充分な接着力を得ることが出来ます。
製作工程 メニュー


**********
ニカワでの固定が確認できましたら、先ずは平ノミ・ナイフ・ヤスリなどで大まかな形状をつくります。
この段階で仕上げることのできる部分は、糸巻き箱の内側につながる部分のみで上記厚みの6mmを削り出します。これに伴って、弦が糸巻きに巻かれる進行状態を想像してナットの上で弦が無理のないような動きになるように傾斜を付けます。ただし6mm以外はまだ十分な余裕を持たせておきます。


**********
指板の先端とナットの両サイドが段差のないようナットの左右を削ります(丸のみ及びヤスリの使用が良いかと思います)。
これにより、ナットの幅が決まりますので(24.0mm~24.5mmの範囲で)弦がとおる溝を付けることが出来ます。溝はG線とE線の間隔を17mmにしてナットの中心より振り分けるようにします。その間の2本(D線、A線)の溝は4本の弦の間隔が均等になるようにセットします。従って、17÷3≒5.7mm
間隔で刻み目を入れることになりますが、実は弦の太さの関係もあり気持ちだけ(?)低音の太い弦の方の間隔を広げると4本の弦のセッティングが自然に感じられます。下の画像は、目立てヤスリで印をつけた後、大まかに溝を作った状態ですが最終的には溝の深さ・幅を弦の太さに合わせて仕上げます。
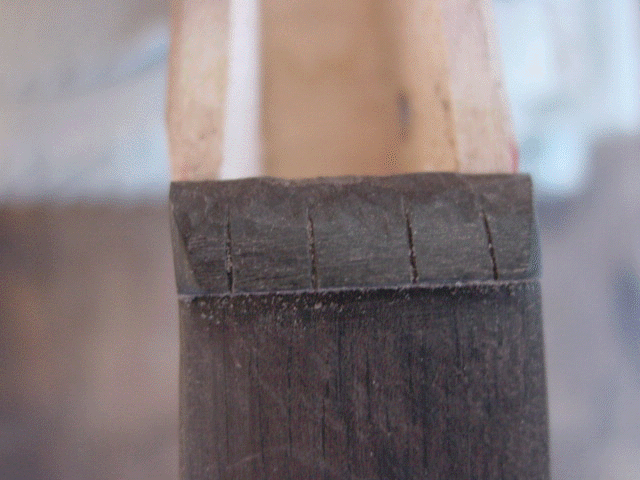

**********
以上の加工の後に、ネックおよび指板のサイドの仕上げ、そしてナットの最終仕上げを行います。
ネックについては、演奏時に親指が当たる部分、いわゆる棹の背面とボタンにつながるR形状およびナット下のR形状、そして指板については、両サイドのエッジの丸み処理をします。この指板の両サイドの処理を行うときに、指板の延長の形状としてナットの幅方向の両サイドの仕上げを行い、さらに糸巻き箱の外形形状を仕上げます。これらの作業はバイオリンが白木の状態で完成するまえの最後の作業としているため、この時点では溝も含めて完成した状態には仕上げてありません。上のナットの画像もまだ未完成の状態のものです。
因みに、バイオリンとしての機能をよく考えられて作られたナットは、小さなパーツではありますが姿としても美しい形状をしています。